menu
menu

BLOG
第8回大阪SJCDレギュラーコース
午前は
大森先生、松川先生から、少数歯補綴物上部構造の講義がありました。
インプラント補綴にはクラウン・ブリッジ、ボーンアンカードブリッジ、インプラントオーバーデンチャー、インプラントサポートがあり、印象法にはオープントレー法、クローズトレー法があり、アバットメントにはスクリュー固定、セメント固定、規制アバットメント、カスタムアバットメント、チタン、ジルコニアアバットメント、それぞれの利点欠点、適応が分かりました。
米澤先生からインプラントのトラブルについての話がありました。
インプラントのトラブルには手術にまつわる偶発症、治療後に起こる合併症、患者とのコミュニケーション不足によるトラブル、患者さんとのコミュニケーション不足によるとらトラブルがあり、併発症、合併症、偶発症の意味の違い、補綴物の合併症のうち、インプラント自体の機械的な合併症、患者さんの因子(パラファンクション、ブラキシズム、メンテナンスに来ない)術者の因子(補綴物、不適切な材料の選択や操作、技術)、生物学的合併症(プラークによる周囲炎、喫煙、糖尿病、BPs製剤、金属アレルギー)
午後からは
技工士さん藤本さん&藤尾さんから補綴物形態の講義がありました。
SJCDのテクニシャンコースのインストラクターをされている方だったので、かなりマニアックな話でしたが、普段、補綴物は技工士さんにまかっせきりで、調整が少ないものを作製してほしいと思っていますが、同じコンセプトでいいものを作成するには補綴物についてもしっかり学ばなければ行けないと思いました。また技工士さんが作製しやすい形成やデザインをする大切さを感じました。
機能的で審美的で清掃しやすい歯周組織から無理なく立ち上がる、
炎症のコントロール(咬合の安定、構造力学的安定)、炎症のコントロール(清掃叢生に優れた補綴物形態)
軸面は清掃性(エマージェンシーロファイル、クラウンカウンツア。トラディショナルエリア、プロキシ丸コンタクト、アンプラジャー)
咬合面は力のコントロールに重要で、静的咬合の安定(顎関節の安定、咬頭嵌合位の安定)、動的な咬合の安定(生理的基の安定、非生理的機能の対応)適切なバーティカルストップ(クロージャーストッパー、イクオライザー、ABCコンタクト)アンテリアガイダンス
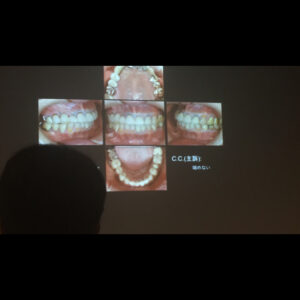

執筆・監修者

院長:医療法人AKATSUKI 理事長:柴田 暁晴
所属学会海外で研鑽をつんだドクターが対応
当院は国際的にインプラント・オールオン4治療で有名なDr.アレックスの元、Dr柴田、Dr近藤ともに世界レベルの歯科医療を学び、地元岐阜可児にてその技術を提供しています。
骨が少なくてインプラント治療を断られたり、入れ歯やブリッジを勧められるケースでも、ほぼ全てのケースでインプラント治療が可能です。

「難症例」であっても対応できる設備とチーム
しばた歯科可児おとなこども矯正では、一般的な矯正治療では対応が難しいとされる“難症例”にも、専門的な診断と高度な設備を活用して対応しています。
歯や顎の状態を精密に把握するために、3D画像診断が可能なCTや口腔内スキャナーを導入。治療前のシミュレーションを行うことで、より安全で的確な治療計画を立てることができます。
また、矯正・インプラント・口腔外科・補綴など、各分野に精通したドクターがチームを組み、複雑な症例にも連携して対応。お子さまから成人まで、他院で「難しい」と言われた症例でも、しばた歯科では最適な治療方法を提案いたします。


© 2025 shibatadental.com